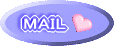◆イスラム教 3
◆イスラム教 3こちらで生活するにあたって、日本では理解できない不便なことがたくさんあります。例えば、女性はコートやスカーフ、チャドルで体を覆わなければならない、豚肉・酒類の飲食・飲酒の禁止などです。
そのような不思議(イスラム圏以外の人々にとって)なことが誰によって、どのように定められているのか、また、法律の位置づけはどうなっているのかを知りたくなります。そして、調べてみるとたくさんの興味深い事が分かりました。
(5)聖法シャリーア
シャリーアは、モスリム(イスラム教教徒)個人の「宗教的」生活、「現世的」生活を具体的に規制する聖法、イスラム法です。そして、それは基本的には国家を越えて存在しています。つまり、国は行政を行うために存在する枠であって立法権や法権はこのイスラム法によって考えられているのです。
コーランは聖法ではないのかという疑問があるかもしれませんが、コーランは聖典であって、それは人間の宗教的道徳意義を述べていて、聖法そのものではありません(後述するが関係はある)。
では、シャリーアには具体的には何が書かれているかというと例に挙げた事柄や以前紹介したイスラム五行、葬儀、結婚、離婚、契約、売買、訴訟、裁判、刑罰、戦争の公私の法規範などが書かれています。もっと具体的に例を挙げると結婚については一夫多妻を認めること(妻は四人まで)や契約では、利子の禁止などがあります。
次に、シャリーアがどのように定められたかという問題ですが、シャリーアはコーラン(聖典)、スンナ(範例)、キヤース(類推)、イジューマ(合意)から成り立っています。そして、コーラン を基礎にして、ハディース(予言者のコーランの解釈法、予言者の言行についての伝承)のスンナから、キヤースによって具体的な例に対して神の意志を引き出し、各地域のイジューマが得られて成立しています。つまり、シャーリアは神の啓示を予言者を介し、人間が解釈したもので、理念は神の意志・命令なのです。そして、シャーリアは変えることができないのですが、社会情勢の変化に応じて人間の解釈を変えることができるという少し、分かりにくいこともあるようです。(現在スンニー派では4つの学派が正統とされている。)
裁判を行う場合は、具体的な事例を法学者や裁判官がシャーリアを適用できるように解釈し、そして、行政府がそれを執行することになっています。具体的な事例と刑を挙げると、背教に対する死刑、飲酒に対する80回のむち打ち刑、私通、姦通の場合は、石で頭を叩き割られて死刑などがあります。 しかし、先にも述べましたが裁きはシャリーアの解釈の仕方によって異なるので、先生の住んでいるテヘランでは、革命後2、3年ほどはむち打ち刑などが路上で行われていたそうなのですが、現在ではそのようなことは見られません。また、「利子の禁止」については、銀行では利子をボーナスと言い換えて、営業しているのが現状だそうです。
シャリーアには、モスリム以外には理解できない事がありますが、それはムハンマドが生きた時代が戦乱中だったことが原因だと考えられます。